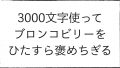多恵は、またしても電車の見える部屋に住むことにした。
幼い頃から電車が好きだった。車種や型なんかはよくわからない。
母親が言うには、ぐずついたり泣き出したりしたとき、祖母の背中におぶさって線路の近くまで行き、電車のガタンゴトンと走る音や踏切のカンカンとなる音を聞くと、次第に泣き止んでいたそうだ。
背中の温かさや、陽だまりの線路沿い、フェンス際に生えている草の感じとかはなんとなく覚えている。
その時住んでいた家から、えんじ色の電車に乗るのが好きだった。母親の買い物についていく。
車内は広く、落ち着いているが、彼女はうきうきして落ち着かない。手に触れる座席の肌触りがいい。行儀悪く靴を脱いで、座席に膝立ちをして、車窓から見る景色は都会なのに田舎みたいで、木々は緑々しかった。
そんなんだから、電車の駆けていく音が、多恵にとっては心地のいいアンビエント・ノイズである。外から姿を見ると、かっこいいなぁ、などと思う。座席に座れば、ゆりかごのように眠気をもたらしてくれる。
電車をぼうっと眺めていると、過ぎた日のことを白昼夢を見るように思い出すことがある。そういう刷り込みなのである。
–
例えば、大学受験に失敗し、浪人していたときのこと。
電車で予備校に通っていた。周りには、いつ勉強をしているのだろう?と思うほど遊んでいる人たちや、浪人であるにも関わらず恋にうつつを抜かす人たちもいた。
幸いにも、多恵にはその余裕はなかった。自分があまり器用ではないことを、そろそろ分かっていた。
引っ越しを何度か経験したからだろうか、一人遊びが得意なタイプなので、黙々と勉強をする孤独感は彼女にとって辛いものではなかった。
空調の効いた部屋で、朝から晩まで、季節もよくわからなくなるほど、よく頑張っていたと思う。
予備校からほど近い喫茶店の軒先に、年老いた犬がいた。
彼は柴犬らしく気高かくて、穏やかだった。もう目は見えていなかったが、キャアキャアと可愛がる若者の群れには、伏せたまま、しっぽを一振りサービスしてみせた。優しく物静かで貫禄のあるおじいちゃん犬だった。
多恵はその喫茶店のオムライスが好きだった。平日のお昼は浪人生やサラリーマンで混み合う。だから、講義のない日曜日の昼下がりが狙い目。
軒先にて、彼の目の前でしゃがみ、彼だけが理解してくれそうな、たわいもない独り言をし、ひと撫でして、自分だけのためにくれるしっぽの一振りをもらってから、お店に入ってケチャップオムライスを食べることが、自分への小さなご褒美だった。
ある模擬試験を終えた日、ふと喫茶店の前を通ると、彼はいなくなっていた。なんとなく嫌な予感はしていた。
つくつくぼうしの鳴く頃、軒先に店主の字で感謝の言葉が書かれた紙が貼ってあり、彼がこの世からいなくなってしまったことが分かった。
季節の移ろいを感じた。それから、悲しくなった。そのときばかりは、気持ちを伝える適当な相手がいない孤独を寂しく思った。もしいたとしても、何をどう伝えただろうか。
葬式というものはよくできている。感情の高まりと緩和を繰り返す。大人たちは酒を飲みかわす。短期間に何度も感情を揺さぶられ、疲れることによって、悲しみに諦めもたらしてくれるシステムなのである。
でも、それとは異なる今回は、悲しみを諦めるための儀式が必要だった。
何をどうすればいいのだろうと思っていたが、口が先に動いた。多恵は、あしたは予備校に行かないから、と母親に言うと、理由を訊くこともなく、いいよ、と言ってくれた。普段からの真面目が功を奏した。
明くる日は晴れていた。そう遅くない時間に目が覚めていたが、ベッドを出たらもう昼だった。台所のサンドイッチのラップをほどく。家族は仕事や学校に出掛けている。
今からのこの時間を、誰もいない家で過ごすのだけは難しいと思った。
とりあえず家を出て、電車に乗る。いつもと違う方向へ。えんじ色の電車から、銀色の電車に乗り換えて、それから緑色の電車にしばらく乗って、また乗り換えて南へ。
平日の電車には人まばら。ときどきシートの肌触りを確かめたり、腕や足を組んだり。ゆらゆら揺られながら、車窓から差し込む午後の光を浴びながら。
うつらうつらと、イヤホンでアジカンやフジファブリックなどを聴いていたら、終着駅に着いた。
駅を出ると、昭和から時間が止まったままのような街だった。一番若いのは自分なのではないか。やっているのかやっていないのかよくわからない商店街だな、と思いきや、しれっと開いている店で乾物や大福が売られていたりする。落ち着く。
しばらく歩くと、やがて海に辿り着いた。夕方の手前、遠くの防波堤に釣り人が何人かと、数羽の海鳥と、遠くに船が見える以外は、静かな海。ちょうどいいと思った。
堤防によじ登った。空と海の間あたりを眺めながら、ぬるい潮風に気持ちを溶かすように、しばらくぼぉっと座って、いろいろなことを思った。
次の日、予備校に向かう途中、喫茶店の軒先で、手を合わせることができた。でも、オムライスを食べに店の中に入ることはもうなかった。
–
しばらくして多恵は大学生になった。家賃が安かったので選んだ部屋の窓からは、電車が見えた。
4年間というものはあっという間だ。細かいことや都合の悪いことはあまり覚えていない。人生を終えるとき、走馬灯になるんだろうな、と思う場面は山ほどある。
単位を落としたこともあったし、別に思い出したくもないような恋もいくつかした。友達と遊んでいるときのほうが楽しかったと思う。
ある大晦日。友達の家に集まって、紅白なりお笑いなりを観ながら、お酒を飲んで談笑していた。気づけば年を越していた。
このまま朝まで笑っていても良かったのだが、友達の一人が、初詣に行こうよと言うと、皆やぶさかではなかった。
終夜運転の電車で2駅ほど、そこまで混雑していないという穴場の神社へ向かった。といはえ年明け早々。鳥居をくぐれば、本殿に向かって参拝客の行列が出来ている。
ダウンジャケットやコートで着ぶくれした人々の後ろに並ぶ。空気はキンと冷たいが、両脇に並んだ屋台がにぎやかで、暖色の灯りが活気を呈している。
焚き火や、どこからか笛の音が聴こえるなど、いかにも正月らしい。俵万智よろしく、「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさなどを感じる。
お賽銭を入れ、神様を呼び出して、手を合わせ、何を祈ったのかは覚えていない。おそらく、当たり障りのない何かだろう。まれにすがるだけの神様にそんなに多大なお願いはできないなとか、ややこしいことを考えてたかもしれない。
それから、おみくじを皆で引いた。全員引き終わるまで、中身は見ない。すこし明るいところに集まって、いっせーのーせ!どん!と紙をひらく。
すると、7人のうち3人が凶だった。多恵もまた凶だった。正月なのに手加減のない神社だね、と笑った。
それからしばらくして解散した。
一人で家路をたどる途中、踏切の中で少し立ち止まった。
明けそうにない、星がいくつか見える空を一通り眺めて、やがて目線を落とす。暗がりから放射状に伸びてくる線路が、街の少しの灯りや作業灯のようなものを反射しているのを、美しいと思ったりもした。
思い返してみれば、その年は、なんだかんだでいい年になったなと思う。
–
多恵が好きなミュージシャンが<愛とはなんぞや>と歌う歌詞の中に「懐かしむこと」とあった。
初期の頃から彼らのことは好きだったが、今の彼らの言葉も違和感なく理解でき、自分もちゃんと歳を重ねていることが実感できて、なお嬉しい。
センチメンタリズムは好きではないが、薄情なのも違うと思う。時折懐古して、今の自分のありようを確かめる時間を悪くないと思う。窓から見える電車を眺めながら、音を聴きながら。
だから多恵は、またしても電車の見える部屋に住むことにした。
–
「3000文字チャレンジ」第76弾【電車】
- このお話はフィクションです。登場人物は架空の存在です
- この記事は、3000文字チャレンジで書きました。第76弾のお題は【電車】
- 公式Twitterはこちら:@challenge_3000
- 中の方のTwitterはこちら:@nakano3000